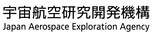宇宙システム解析検証(プロジェクト上流における複合モデルベースデザイン技術の構築)
JAXAスーパーコンピュータシステム利用成果報告(2024年2月~2025年1月)
報告書番号: R24JDG20177
利用分野: 研究開発
- 責任者: 清水太郎, 研究開発部門第三研究ユニット
- 問い合せ先: 河津 要, JAXA研究開発部門第三研究ユニット(kawatsu.kaname@jaxa.jp)
- メンバ: 藤本 圭一郎, 河津 要, 岡田空悟, 辻真次郎, 大木 優介, 椿直人, 西村彗
事業概要
近年, 宇宙分野においてもMBD手法による開発の効率化やデジタル化による開発プロセスの刷新が進められつつある. JAXA研究開発部門第三研究ユニットでは, 開発上流段階での宇宙システムの設計開発の効率化を目的として, 複合物理モデル・システム統合シミュレーション技術を活用したMBD手法の構築・適用を進めている. 本事業では, このMBD手法の適用として, パラメータスタディやモンテカルロシミュレーションのような膨大なケース数のシミュレーションをJSS3上で効率的に実行することで, 宇宙システムの設計成立性やリスク評価を実施している.
参照URL
「システムレベル設計・検証技術|第三研究ユニット(旧 情報・計算工学センター)」参照.
JAXAスーパーコンピュータを使用する理由と利点
・JAXA職員であれば煩雑な手続き無しでクイックに利用可能であること
・JAXA内のシステムであるため, 同じJAXAイントラネット内で接続可能であり情報流出のリスクが少ないこと
・開発中の宇宙機の設計情報のような機微情報をJAXA内で閉じて取り扱えること
・システム使用方法について手厚いサポートがクイックに受けられること
・豊富な計算資源を活用して多数のモンテカルロシミュレーションを短時間に実施可能なこと
今年度の成果
宇宙機自動ドッキング機構を対象に, 複合物理モデル・システム統合シミュレーション技術を活用し縮退モデルを構築した. さらに, JAXAスーパーコンピューターシステムでの多数ノード同時並列計算により, これまで困難だった膨大なケース数の解析を可能とした. 本アプローチは自動ドッキング機構の設計成立性評価や安全化方策のトレードオフにおいて活用された.
成果の公表
-口頭発表
Kaname Kawatsu, Hirofumi Kurata, Hikaru Mizuno, "Multi-disciplinary model-based development method targeting spacecraft automated docking systems," AAS/AIAA Space Flight Mechanics, 2025.
JSS利用状況
計算情報
- プロセス並列手法: 非該当
- スレッド並列手法: 非該当
- プロセス並列数: 1
- 1ケースあたりの経過時間: 30 分
JSS3利用量
総資源に占める利用割合※1(%): 0.04
内訳
JSS3のシステム構成や主要な仕様は、JSS3のシステム構成をご覧下さい。
| 計算システム名 | CPU利用量(コア・時) | 資源の利用割合※2(%) |
|---|---|---|
| TOKI-SORA | 0.00 | 0.00 |
| TOKI-ST | 300548.45 | 0.31 |
| TOKI-GP | 925.99 | 0.01 |
| TOKI-XM | 0.00 | 0.00 |
| TOKI-LM | 0.00 | 0.00 |
| TOKI-TST | 0.00 | 0.00 |
| TOKI-TGP | 1724.42 | 11.87 |
| TOKI-TLM | 0.00 | 0.00 |
| ファイルシステム名 | ストレージ割当量(GiB) | 資源の利用割合※2(%) |
|---|---|---|
| /home | 163.39 | 0.11 |
| /data及び/data2 | 2433.33 | 0.01 |
| /ssd | 0.00 | 0.00 |
| アーカイバシステム名 | 利用量(TiB) | 資源の利用割合※2(%) | J-SPACE | 0.00 | 0.00 |
|---|
※1 総資源に占める利用割合:3つの資源(計算, ファイルシステム, アーカイバ)の利用割合の加重平均.
※2 資源の利用割合:対象資源一年間の総利用量に対する利用割合.
ISV利用量
| 利用量(時) | 資源の利用割合※2(%) | |
|---|---|---|
| ISVソフトウェア(合計) | 0.00 | 0.00 |
※2 資源の利用割合:対象資源一年間の総利用量に対する利用割合.
JAXAスーパーコンピュータシステム利用成果報告(2024年2月~2025年1月)