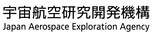大規模惑星集積並列N体計算:衝突破壊を考慮した微惑星集積
JAXAスーパーコンピュータシステム利用成果報告(2018年4月~2019年3月)
報告書番号: R18JACA27
利用分野: JSS2大学共同利用
- 責任者: 小南淳子, 東京工業大学
- 問い合せ先: 小南淳子, 東京工業大学地球生命研究所(kominami@mail.jmlab.jp)
- メンバ: 小南 淳子
事業概要
微惑星どうしの衝突が起こった時, 破片が生成される. その衝突破壊の効果を我々のN体シミュレーションコードに取り入れ, より現実的な円盤の環境での原始惑星の進化を追うことを目的とします.
参照URL
なし
JSS2利用の理由
これまでのN体計算ではGRAPEという重力多体計算専用の計算機を使っても粒子数が3万体が限度でした. しかし, 動径方向に惑星が動くことやアイスラインを含めた広い初期条件から始める計算を行うためには少なくとも10万体ほど必要となってきます. この粒子数を計算するためにはスパコンを使い, 並列計算を行う必要が出てきました.
今年度の成果
初期条件としてKominami et al. (2016) のセカンドステージで使用した初期条件と同じものを使用しました. ガス抵抗とタイプ-1 惑星移動の効果はKominami et al. (2005) で使用した表式を取り入れました. 粒子数が増えることで結果がどのように影響を受けるかを確かめるために, まず, 簡単な破壊モデルをN体計算コードに取り入れました. 小さい破片にはガス抵抗が働きやすく, ランダム速度が小さくなりやすくなります. それらは原始惑星の円盤外側へのPlanetesimal Driven Migration を起こしやすくします. 完全衝突合体の場合では, 外側へ動いている原始惑星のすぐ外側の微惑星が集積を起こし, 大きくなっていくところが, 衝突破壊を考慮した本計算では, 小さい破片(あるいは小さい微惑星)が常に原始惑星の外側にいることになります. Planetesimal Driven Migration というのは, 原始惑星と周囲の微惑星の質量比が~100くらいないと起きない現象です. 完全衝突合体の場合では微惑星の集積が起こることにより, その条件が満たされなくなってしまいましたが, 衝突破壊を考慮した場合は, その条件は常に満たされ, 外側のplanetesimal driven migration が続いていくという結果になりました.
成果の公表
なし
JSS2利用状況
計算情報
- プロセス並列手法: MPI
- スレッド並列手法: OpenMP
- プロセス並列数: 32 - 168
- 1ケースあたりの経過時間: 60 時間
利用量
総資源に占める利用割合※1(%): 0.00
内訳
JSS2のシステム構成や主要な仕様は、JSS2のシステム構成をご覧下さい。
| 計算システム名 | コア時間(コア・h) | 資源の利用割合※2(%) |
|---|---|---|
| SORA-MA | 11,368.36 | 0.00 |
| SORA-PP | 0.00 | 0.00 |
| SORA-LM | 0.00 | 0.00 |
| SORA-TPP | 0.00 | 0.00 |
| ファイルシステム名 | ストレージ割当量(GiB) | 資源の利用割合※2(%) |
|---|---|---|
| /home | 4.77 | 0.00 |
| /data | 47.68 | 0.00 |
| /ltmp | 976.56 | 0.08 |
| アーカイバシステム名 | 利用量(TiB) | 資源の利用割合※2(%) |
|---|---|---|
| J-SPACE | 0.00 | 0.00 |
※1 総資源に占める利用割合:3つの資源(計算, ファイルシステム, アーカイバ)の利用割合の加重平均.
※2 資源の利用割合:対象資源一年間の総利用量に対する利用割合.
JAXAスーパーコンピュータシステム利用成果報告(2018年4月~2019年3月)